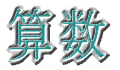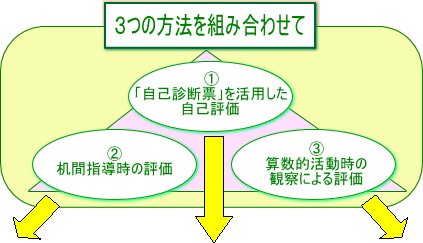| 総論 |
国語 |
社会 |
算数 |
理科 |
生活 |
音楽 |
図工 |
家庭 |
体育 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
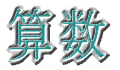
算数科における評価のポイント
―― 1単位時間内における評価の工夫 ――
 トップページへ
トップページへ 

 算数科ファイルを見る
算数科ファイルを見る
はじめに
この算数編では、毎時間の授業に生かせる「1単位時間内での評価」について紹介します。
理論編には、その必要性と具体的方法について、実践編では、理論編であげた評価方法の実践例を紹介します。資料編には、この実践に関わる指導案等の資料をのせました。
理論編
I 1単位時間内の評価は、なぜ必要か?
1 算数の特性とは?
○ 系統性と積み重ね、そして、発展
算数には、内容の系統性が明確であるという特性があります。他の教科についてもいえることですが、とりわけ算数科においては、基礎的・基本的な知識と技能を確実に定着させながら、
それをもとに新しい学習を積み重ね発展させることが大切です。つまり、毎時間の学習内容の確実な理解がその積み重ねを可能とするわけです。
○ 算数的活動を通した主体的な学習
さて、もう一つの特性として、 算数科の目標
にある「
算数的活動 を通して、・・・・・・活動の楽しさや数理的な処理のよさに気付き・・・・・・」という点があります。算数の学習における楽しさや充実感は、算数の内容や本質に関わる重要な要素です。
つまり、児童が主体的に算数的活動に取り組むことよって、算数の学習を身近で楽しいもの、役に立つもの、自分たちでつくることのできるものとしてとらえられるようにすることが重要なのです。そうあってこそ、本来の算数科のさらに充実感・満足感を味わったり、美しさなどに感動したりできるものにしていこうということなのです。
資料1
学習指導要領算数の目標
数量や図形についての算数的活動を通して、基礎的な知識と技能を身に付け、日常の事象について見通しをもち筋道を立てて考える能力を育てるとともに、活動の楽しさや数理的な処理のよさに気付き、進んで生活に生かそうとする態度を育てる。
-小学校学習指導要領より- |
資料2
算数的活動
児童が目的意識をもって取り組む算数にかかわりのある様々な活動の総称。
作業的・体験的な活動など手や身体を使った外的な活動を主とするが、思考活動など内的な活動を主とするものも含まれる。
・手や身体等を使って、ものを作る活動
・教室の内外において、各自が実際に行ったり確かめたりする活動
・身の回りにある具体物を用いた活動
・実態や数量などを調査する活動
・概念、性質や解決方法などを見付けたり、つくり出したりする活動
・学習したことを発展的に考える活動
・学習したことを様々な場面に応用する活動
・算数のいろいろな知識、あるいは算数の様々な学習で得た知識などを総合的に用いる活動
-小・中学校授業改善ハンドブック(H12,3月/京都府教委)より-
|
2 算数の特性からみた評価のあり方
○ 毎時間の評価、1単位時間内の評価が重要
系統性が明確で、基礎・基本を確実に積み上げていくことが大切な算数科においては、毎時間の評価がことのほか重要です。つまり、1単位時間内の学習事項が、学習過程の各時点においてどの程度理解できているのかを、個々の児童について的確に見取る評価を重視する必要があるということです。
○ 算数的活動における児童の変容を見て取ることが必要
一口に
算数的活動 といっても、学年や単元領域によって多様な活動が考えられます。しかし、そこで大切なのは、「どういう意図をもってその活動を設定したのか」ということと、「その活動から、どのような児童の変容を、いかにして見て取るか」ということです。ただ単にできたかどうかということだけではなく、その活動をとおして、児童一人一人がどう考え、どう気づき、どう楽しみ、どう充実感を得、その結果どう変容したのか等々のことをつぶさに見て取ることがもっとも大切です。、そして、そのためには、教師側にそれらを見て取る力とそのための具体的方法をもつことが必要です。
資料3
発展的な学習
学習指導要領に示す内容を身に付けている児童生徒に対して、個に応じた指導の充実を図る観点から、児童生徒の興味・関心等に応じて、学習指導要領に示す内容の理解をより深める学習を行ったり、さらに進んだ内容についての学習を行ったりするなどの学習指導であるといえる。児童生徒の理解や習熟の状況等に応じ、指導内容を適宜工夫することが求められているが、その際、学習指導要領に示す内容と全く関連のない学習や児童生徒の負担過重となるような指導にならないようにすることに留意する必要がある。
補充的な学習
全ての児童生徒が基礎・基本を確実に身に付けることができるようにすることが重要であり、補充的な学習とは、
児童生徒の理解や習熟の状況等に応じ学習指導要領に示す基礎的・基本的な内容の確実な定着を図るために行う学習指導であるといえる。
各学校にあっては、個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、ティームティーチングなど様々な指導方法や指導体制の工夫改善を進め、
当該学年で学習する内容の確実な定着を図ることが重要である。
-小・中学校授業改善ハンドブック(H15.3月/京都府教委)より- |
 ページの先頭へ戻る
ページの先頭へ戻る
Ⅱ 1単位時間内の評価をどう行うか?
1 評価方法を考えるに当たって
○ 児童の学習意欲を引き出し、「自ら学ぶ力」を育てる評価となること
評価本来の目的は、「児童の意欲を引き出し、よりよい学習を導くこと」にあります。ですから、評価方法を工夫する際には、
その方法が「自ら学ぶ意欲」の育成に役立つものであるかどうかという視点がまず必要です。
○ 指導と評価の一体化につながるものとなること
一人一人の児童の学習状況を的確に評価し、その結果が、スムースに個に応じた指導に生かされるものでなければ意味をなしません。 そして、
「発展的な学習」や「補充的な学習」へとつながっていくように工夫することが大切です。
○ 評価のための評価とならないこと
必要以上に時間と労力のかかる方法は、継続性がないばかりか、結果的に児童への指導に生かしきれなかったり、
いわゆる「評価のための評価」に陥るおそれがあります。
○ 実現可能な具体的方法となること
行き過ぎた評価規準の詳細化や評価方法の多様化は、机上の空論となってしまい、実際には活用できないものになるおそれがあります.
2 具体的評価方法の工夫(その概要とポイント)
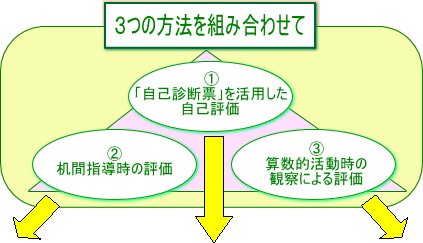 |
|
② 机間指導時の評価 |
① 「自己診断票を活用した自己評価」 |
③ 算数的活動時の観察による評価 |
|
|
<概要>
これは、従来から行われている机間指導に、 「すべての児童に対して、評価を行う」という役割を明確に位置づけたものです。これまでは机間巡視とも呼ばれ、 気にかかる児童に個別指導を行うものでした。
しかし、この方法では、児童が自力解決している時に、すべての児童のノート等を見て回りながら、
適切な評価の言葉かけをするという評価活動をはっきりと位置づけた点で、従来の机間指導とは性格的に異なっているといえます。 |
<概要>
現在よく見られる「ふり返りカード」を使った自己評価は、授業の最後にその学習をふり返って記入するものが多く見られます。
しかし、この方法には、「各学習事項について理解が困難な児童にタイムリーに支援することができない」という問題点があります。
そこで、学習過程のそれぞれの段階において、自分自身の問題解決の度合いや理解の程度をチェックすることができるカード「自己診断票」を用意することにしました。
児童はこのカードにある各学習事項について自己診断結果を記入し、机上においておきます。
これを教師が見て回りながら、個に応じた指導を行うというものです。 |
<概要>
算数的活動とは、算数にかかわりのある作業的・体験的活動(思考活動も含む)等をさします。これは、数量や図形について理解したり、
感覚を豊かにしたりするなど、学習活動の一つとして位置づけられており、この活動を通して、児童は自己の能力を発揮し磨き、
あらたな力を身に付けていきます。
そこで、この活動中に現われる児童の実態や変容ぶりを、具体的視点を明確にして見て取ろうということです。 |
|
|
<ポイント>
①児童が自力解決した結果に対して、即時に評価し適切な言葉かけ(賞賛、発展課題の示唆、つまずきの原因のヒント等々) をすることにより、学習への意欲が高まります。
②児童個々の学習状況が的確に把握できるので、より的確な個に応じた指導が可能になります。 |
<ポイント>
①自己診断票に基づき学習を進めることによって、児童が本時のねらいを明確に自覚し、見通しをもった主体的な学習をすることができます。
②児童自身が自己診断することにより自己評価能力が高まり、「生きる力」の育成につながります。③児童自身の自己診断と指導者側の評価を総合することで、 より的確な個に応じた指導が可能になります。 |
<ポイント>
①算数的活動を意図的に設定することで、学習上の効果が望めるばかりではなく、継続的に観察することにより、
個々の児童の「関心・意欲・態度」の力を把握し評価することが可能になります。
②複合的な技能や能力を必要とする場面を設定して観察することにより、 個々の児童の「思考・判断」の力を把握し評価することが可能になります。 |
|
|
|
|
|
|
 トップページへ
トップページへ
 ページの先頭へ戻る
ページの先頭へ戻る