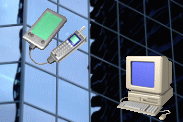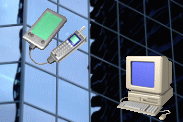| 指導のねらい |
| (1) |
実例を通してマルチ商法・ネズミ講がどのようなものかを理解させる。
|
|
|
| (2) |
ネットワークを利用した勧誘などにあった際の対処方法を理解させる。 |
|
| 指導の手引 |
| ・ |
怪しいと感じた電子メールやWebページに出会った場合は、うのみにせず、いろいろな人に相談するなどして細心の注意を払うことが、自分の身を守ることにつながる。
|
・
|
特にネズミ講、マルチ商法は、金銭上や人間関係上のトラブルが生じやすい問題なので、知人や友人を誘うことにより信頼関係を失ったり、知らぬ間に法律違反を犯すなど、取り返しのつかないことに発展する危険性が高い。
○ね ず み 講(無限連鎖講)
後順位の加入者が支出した金品を、先順位の加入者が受領することを目的とした配当組織で、加入者が無限に増加することが前提条件となっており無限連鎖講ともよばれる。ねずみ講の防止に関する法律により ねずみ講を開設した者も参加した者も罰せられる。
○マルチ商法
販売組織の加盟者が次々に消費者を組織に加入させ販売員とすることにより、組織をピラミッド式に拡大していく商法のこと。販売員となった消費者は、売れない商品を抱えたり、不必要な商品を大量に購入させられるなどの問題が生じやすいことから、このような販売方法そのものが禁止されているわけではないが、「特定商取引に関する法律」により「連鎖販売取引」として規制されており、広告規制、契約書面の交付義務、クーリングオフ制度等が設けられている。
※ ねずみ講とマルチ商法の違い
ねずみ講とマルチ商法は類似しているが、マルチ商法は特定の商品の再販売等を行うことにより、加入者がマージンを受け取る組織的販売方式であり、適切な組織運営を行えば事業を維持することは可能であるのに対し、ねずみ講は生産的な活動を伴わない金品配当組織であり、新しい加入者の勧誘が必ず行き詰まり、組織の維持が不可能である点でマルチ商法と大きく異なる。
このようなことから、マルチ商法は法による規制は受けているものの禁止されていないのに対し、ねずみ講は法により、開設、運営、勧誘等の行為が一切禁止されている。
|
<参考>
警察庁「インターネットトラブル」
http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm
|
展開例
|
|
学習活動
|
指導上の留意点
|
| 1 |
本時の学習のめあてを知る
|
| 2 |
ワークシートの事例を読む
|
| 3 |
思ったことを書いてみる
|
| 4 |
友達やグループで「悪質商法への適切な対応」について話し合う
|
| 5 |
意見をまとめて数人が発表する
|
| 6 |
自分の感想や意見を書く
|
| 7 |
本時の学習をまとめる
|
| 8 |
自己評価をおこなう
|
|
(Webページを使った体験的な学習活動を取り入れる場合は2と3の部分を活動にあてる)
| ・ |
場合によっては、加害者や被害者になることがあることを理解させる。
|
| ・ |
ネズミ講やマルチ商法のしくみを理解させるだけでなく、どこが問題なのかを考えさせる。 |
|
| 発展的な学習 |
| ・ |
ネズミ講は「無限連鎖講の防止に関する法律」で禁じられていることを理解させる。 |
|
|
|
|
一覧表へ / 前のページへ / 次のページへ

京都府教育委員会
|
| ●ダウンロード |
| 左のページを下記のファイル型式でダウンロードして御利用いだくことができます |
 Wordファイル Wordファイル |
 PDFファイル PDFファイル |
| ●投稿コーナー |
この資料に関する御意見や御感想をお寄せください。
京都府教育情報ポータルサイト内「情報モラル」会議室へ |
|