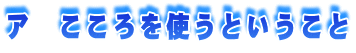相談に来られる教師とお会いしていると、「登校できない子」への教師の関わりが、心理臨床家の行う心理療法やカウンセリングのいわば「表面的な真似事」に陥ってしまっている現実が少なからず学校にはあるように感じています。
学校教員としてのアイデンティティに揺れをみせてしまう教師も少なからずあるようにも思われます。
カウンセリングの技法や手法を学ぶことで、子どものこころがわかったかのような錯覚を起こしてしまうこともありますが、これは子どもに「こころを使っている」のでなく、「頭を使っている」状態です。
学校教育相談において登校できない子どもへの対応にあたっては、ただ単にスクールカウンセラーや心理臨床家、精神科医からの指示や指導されたとおりに、子どもに「指示しない」ことだけが絶対視されがちで、実際のところ子どもは「放置」されていることもあります。
これは親も同じであり、叱っても説得しても登校できないとなると「待つしかない」となって、「放置」されてしまっているような場合もあります。
また、子どもの語る内的事実にジッと耳を傾けている心理臨床家のカウンセリングを「甘やかし」や「迎合」と誤解して、学校でも表面的に同じように何でもかんでも「そうか、そうか」と安直な非指示的な関わりがステレオタイプになされていたりすることもあります。
ここでは「放置」が悪いとか駄目だということを強調しているのではなく、そこに潜む問題点について明確に知っておくということが必要であると考えています。
結果的に子どもは教師に「放置」されたことによって、ゆっくりと回復に向かっていった例もあるわけで、個々のケースによっても異なり、また生身の人間のこころの中のことですから、一概にその関わりの良し悪しということをここで論じようということではありません。
教育相談所などで行う心理臨床家の個人に対する心理療法や一対一で行うカウンセリングの理念と実践は、教師の行う支援とは異なっており、相談室や保健室で行う学校教育相談のパラダイムにそのまま姿で置き換えるのは難しいものです。
大事なことは、子どもに「こころを使う」ということです。
では、「こころを使う」ということは、どのようなことなのでしょうか。