2 不登校への早期対応・早期の解決
(1) 不登校のとらえ方の変遷
不登校への早期対応・早期の解決のためには、学校や家庭において「不登校」ということが、今、どのようにとらえられているのかについて知っておくことは、とても大事なことであると思います。
「不登校」は、学校の問題なのか、家庭の問題なのか、あるいは本人の問題なのか。時代とともにそれはどのようにとらえられてきたのでしょうか。
平成16年度第2回SSN研修会(平成17年1月実施)において、京都教育大学 教授 本間友巳先生が「学校復帰のための支援と効果的な訪問指導の在り方について〜不登校の未然防止と解決に向けて〜」と題して、不登校のとらえ方の変遷について講義をされました。
「不登校」そのもののとらえ方、理解の仕方が、その時々の時代によってどのように変化し、どのように対応されてきたのか、本間先生のご了解を得て、講義内容の一端を抄録にて紹介します。
*************************
不登校の理解に関わって、どのように理解されてきたのかを理解すること。これは「メタ理解」、または「メタ認知」とも言いますが、どのように不登校が理解され考えられてきたのかについて、まず話させていただきたいと思います。
問題が起こったとき、なぜそれが起きたのか、私たちは原因を考えることが多くあります。これは原因論がその柱としてあるわけです。不登校の問題を考えるときに、その原因を、一つには家庭や本人に向けて考えようとする考え方があります。子ども家庭志向とでもいえるでしょう。もう一つは、学校とか社会の方に原因があるのではないかという考え方があります。これは学校・社会志向といえるでしょう。この二つの大きな軸の、両極のなかに私たちの意識があるのではないかと思います。
この「原因を考える」ということと、もう一つ、「どう対応するか」ということの二つの軸を考えてみます。
不登校に関して言えば、「どう対応するか」ということを大きく分けるとすれば、これも2つの極が考えられます。1つは学校に来させる、つまり学校復帰とか再登校という考え方です。学校に向ける方向で指導や援助する対応のスタンスがあります。もう一方は、学校はもういいんだという考え方です。不登校に対応する専門的な考え方にそういう考え方もあります。脱学校、極端だと反学校という考え方です。学校には頼らなくていい。子どもが学校へ行かないのは学校の方に問題があるので、学校というものをない状態にして、違うところで子どもを育てようとする考え方です。どちらかというと学校に近づけるよりも遠ざける考え方です。
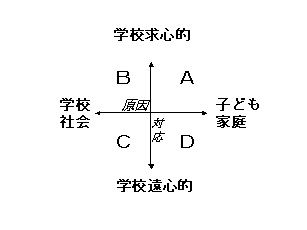 これを図にしてみると、典型的な例として「A」にあたるところは、学校に行かせる方向で、原因論として家族や子どもの問題の方が大きいという認識に立つ考え方です。これは不登校に対する1つの典型的な考え方であったし、歴史的に見てもかなり強くあったと言えます。無理してでも引っ張り出してもいいということもあったわけです。
これを図にしてみると、典型的な例として「A」にあたるところは、学校に行かせる方向で、原因論として家族や子どもの問題の方が大きいという認識に立つ考え方です。これは不登校に対する1つの典型的な考え方であったし、歴史的に見てもかなり強くあったと言えます。無理してでも引っ張り出してもいいということもあったわけです。
これと逆に代表的なのは「C」にあたるところです。子どもや家庭よりも学校や社会に問題があるから学校に行かなくてもいいという考え方です。フリースクールはその考え方に差があるので、一概にはこうだとは言えないですが、80年代から登場するフリースクールの多くはこの考え方です。有名な「東京シューレ」などのフリースクールは、「脱・学校的」とでもいうか、無理に学校に戻そうとするなという考え方があったと思います。
保護者も学校や社会に原因を求めやすいですから、保護者の考え方は「C」に入る場合と「B」に入る場合があります。「B」のように学校社会に原因を帰属して、しかも学校に求心的であるという場合には、学校批判となって保護者の思いが表れたりすることもあると言えます。
教育支援センター(適応指導教室)は、ある意味、この「B」の考え方に基づいて設置されてきたと言えるかもしれません。また、医療機関などで行われる「治療モデル」による不登校への関わりは、どちらかというと「D」の考え方に基づいているところが多いのかもしれません。
もう少し、歴史的に不登校が社会でどのように認識されてきたかを考えていきたいと思います。
「不登校」という言葉は、新しい言葉です。教育の中で、しかも行政的に言葉が使われだしたのは、1967年の長期欠席の調査の中に”学校嫌い”という言葉が使われたのが始まりです。当時は、長期欠席と言うと、病気欠席か経済的な理由によるものかというおおざっぱな考え方でした。
年間授業日数の5分の1を目安にして長欠としていました。長欠は戦後の方が圧倒的に多かったのです。それは「不登校」ということではなくて、病気とか経済的理由によるものでした。学校に来られない子どもの8割くらいは経済的理由もしくは病気ということでした。1940年代の中学生の長欠率は6%ぐらいだったと思います。
今、日本では欠席率の調査はほとんど行われていませんが、諸外国では欠席する子どもがすごく多いですから、諸外国では当然のように欠席率の調査が行われています。日本の子どもの欠席率は2%を超えるか超えないかです。諸外国とは学校に対する考え方が違うのでしょう。
1970年代の中頃に、長欠率は中学校でも0.5%ぐらいになって底をうちます。60年代後半からそれらにあてはまらないような欠席のパターンが出てきたのです。それを”学校嫌い”という名称で呼ぶようになりました。”学校嫌い”は長欠率が底をうってから徐々に増えてきました。今日においては中学校の長期欠席の8割が「不登校」。戦後の8割が病気か経済的理由という状況ですからコロリと変わったと言えます。小学校でも「不登校」は5割を超えています。
数が少ないということは、特殊な問題と見られがちです。みんなが学校に来ているのに、学校に来られないということは、子どもや家庭に原因があるのではないかという考え方になります。したがって、何とかして来させようとする働きかけが行われるのです。70〜80年代まではそういう「何としても学校に来させる」という流れであったと思います。不登校対策がとられることはなく、義務教育段階でも原級留置もありました。
日本の学校が変わる一つのターニングポイントは、学校批判が激しく行われるようになった80年代です。そのきっかけのひとつが校内暴力といじめです。メディアを賑わす事件が起き、大きく取り上げられました。そのたびに学校は厳しく批判されてきました。
それに加えて不登校(当時は登校拒否)が増えてきて、学校に戻すということよりも、学校遠心的な動きが民間を中心に起こり始めたのです。フリースクールなどが立ち上がってきました。そうなると不登校への対応の風向きが変わってきました。
1992年(平成4年)に登校拒否調査研究協力者会議が行われ、不登校に対する方針が出されました。「不登校は誰にも起こりうる」ということが言われ、無用な登校刺激をさけて、学校へ戻すことだけでなく、自立を目指す取組を行っていきなさいということが言われたわけです。
それ以降、様々な施策が行われました。ひとつは学校の多様化をベースにした学校改善の動きです。もう一つは学校外にバイパスをつくっていく動きです。バイパスをつくっていく動きの一つは、適応指導教室、教育支援センターの設置です。平成に入った当時、だいたい全国で20〜30箇所ぐらいだったのが、当時の文部省が調査研究で市町を指定していき、今では1000カ所を超えました。
それにともなって適応指導教室への出席を要録上の出席扱いにするということが公認されていきました。また、95年(平成7年)からはスクールカウンセラーが学校に入りました。心理学的なものが学校に入ってきたのです。スクールカウンセラーが学校へ入っていくということは、臨床心理士の受け皿としての組織ができたという意味でも大きいことでした。並行してスクールカウンセラーが入らない学校には、心の教室相談員を配置しました。校内に相談室をつくるということも進んでいきました。また、直接不登校とは関係ないかもしれませんが、高等学校の多様化も進みました。総合学科ができたり、定時制・通信制が整備されました。高校へ行けなくても大学へ行けるようにと大検の受験機会が増やされたり、いろいろな施策が出てきました。その施策が進められるにしたがって、民間レベルでもフリースクールなど、様々なものが出てきたのです。
考え方の流れが、学校にもどす方向でなくて、学校の改善をしながら、そこに入らない子どもは学校外の施設で受け入れるようなことができるようになったわけです。
これが、最近になって少しずつ変化してきています。2003年(平成15年)に、1992年(平成4年)と同じような会議、不登校問題調査協力者会議が行われました。これまでの流れの中では、登校刺激を与えてはいけないとか、学校の話題に触れてはいけないと言われる方向になっていました。そこから肥大して少し行き過ぎた考え方になり、学校では登校支援ができていなくて、「外注」みたいにして、外にお任せになってしまっていた。まず、そのことを変えた方がいいのではないかという流れの中で報告書が出されたのです。そこには進路形成と社会的自立につながるような積極的な働きかけがいるんだということ。放っておいたらいいというものではないということであり、家庭に対してもっと働きかけてもいいんではないかと言われたのです。
このような考え方が広まるようになった背景は3つ考えられます。
一つ目は、虐待の問題です。虐待は家庭内の問題です。これまでは家庭の問題に触れることは難しかったのですが、この問題を通して家庭の中も大変なんだということが言えるようになってきました。
二つ目は、引きこもりの問題。「引きこもり」=「不登校」ではありませんが、確かに引きこもりの中に不登校経験をもった人たちもいるわけです。そのような中で、ただその状態を見守るだけではどうかという考え方がおきてきました。何らかの働きかけをしなければならないという気運が盛り上がってきたのです。
三つ目は、これも不登校とは直接的には関係がないのかもしれませんが、学力低下の問題です。学力の問題が不登校の問題と関係していることがあります。これまでの学力と言うと、受験勉強とか進学率だとかが話題の中心であり、むしろ学力の話題をタブー視する傾向がありました。学力の二極化の問題も不登校に影響しているという考え方から、不登校の子どもたちも自立に向けて学習させることも必要だといわれるようになった。こういうことを含めて、この前の報告書では進路形成と集約されているのです。
つまり、不登校の子どもの自立に向けた働きかけをしていくこと。積極的な関わりをしてもいいんですよということが言われているのです。学校外のものを積極的に取り入れていこうとする流れは変わってはいません。学校に戻すだけでなく、様々なバイパスを使って、社会的な自立をめざそうとしています。その中に学校をいれて、対立的ではなくて協力関係のなかで自立を可能にするということを目指していると思われます。学校内外のコミュニケーションが生まれる素地はできつつあるのではないかと考えています。
このように不登校に対する対応は時代とともに変化してきています。「対応」というのは時代の流れの影響を受けます。私たちの認識も様々な影響をうけて構築されているから、それは変化していくものであって当然と言えます。
70年代の、不登校の子どもを何が何でも学校に戻すという考え方から、90年代の無理をしないという考え方。そして今日の、もうちょっと働きかけようとする考え方という流れをみると、一見、前に戻るような印象を受けますが、もう少し成熟した形で今の不登校への「対応」は進んでいるのではないかと思いますし、また進めていかなければならないと思います。単に昔に戻るのではなく、成熟した形で不登校支援をする必要があると思います。
どちらかと言うと、カウンセリングの考え方、臨床心理学の考え方には、積極的に相手に介入していく考え方はないし、それに上手ではありません。そういうことを支えていく理論はあまりもっていないとも言えます。どちらかと言うと、待って機が熟するの「待つ」というスタイルで子どもや保護者に関わっていこうとします。積極的に働きかけていくのを「介入モデル」とすると、カウンセリングや臨床心理学の理論は、「待つ」という「待機モデル」です。
教師というのは「介入モデル」でこれまでずっと「教育」を続けてきたわけです。
なぜ臨床心理学が「待機」ということを重視するかというと、来られる人がカウンセリングに来てみたいとか、カウンセラーと会ってみたいというような動機付けを前提にしているからです。また、カウンセリングに来られる方を受け入れるための信用というものも前提にあるわけです。カウンセリングとか教育相談では、動機付けがあって、ある程度の信用があって、そこから関わりが始まるという考え方だと思います。
その動機付けや信用を無視して、踏み込んでいって会いたくないのに無理に会ったり、無理に学校に連れて行ったりというのは避けるべきです。
動機付けと信頼は関わりのベースになりますが、それができるようになるためには、ひたすら待てばいいかというとそんなものではないわけです。どうやって動機付けや信頼を作り上げるんだということを考えておく必要があります。動機付けや信頼は初めからあるのではなくて、創っていくものなのであって、関わりのなかで形成していくんだという視点が大事です。ですから、そのための方法を考えるべきなんです。
どうやって信頼とか動機付けをつくるかということは、何を話すのかという内容を考えると難しいんです。いいことや素晴らしいことを言ったとしても、相手がいいなと思ってくれなければ通じないわけです。通じるか通じないかは関係性によるのです。関係性をつくる努力をしなければ通じないと言えます。
私たちは、話す「内容」の方に引きずられがちです。しかし、こちらがどのような話をするかということは、実はそれほど問題ではないのです。こちらがどう思うかということよりも、相手がどう思うか、どのように感じているかという世界なのです。その人が何を求めているかということを感じ取って「関係」をつくることが語る「内容」以上に大事なのです。
また私たちは、相手がしゃべったことに対して、その原因を考えることが多くあります。よく考えれば、人間の問題というのは、ある何かの原因があって、ある行動があるとは限らないのです。原因と結果は見た目の違いにすぎないのです。立つ位置によって原因と結果は入れ替わることもあるし、切断の仕方によって原因は結果にもなるし、結果は原因にもなるわけです。原因を探って理解して、そして何か伝えていこうとするのは、なかなかうまくいかないことが多いのです。
私たちは人の話をどこで聴くのが大事かというと、「語られた内容」に込められた「感情」に焦点を当てるということになるでしょう。その人がそう語ったのは何を伝えようとしたかということです。その人の感情レベルに焦点をあてて、その人のニーズを探っていくという細かいところを考えながら話を聴こうとすることが大切なのです。その中で動機付けや信頼が構築されていくのです。
また、話したい内容をどのように伝えるかということも大事です。普通は軽視されがちですが、ものの「言い方」ということも非常に大事です。そのためには、私たちは言葉をどのように使っていくかを常に頭に置いておくことも必要だと思います。
*************************
indexに戻る
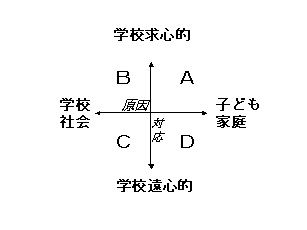 これを図にしてみると、典型的な例として「A」にあたるところは、学校に行かせる方向で、原因論として家族や子どもの問題の方が大きいという認識に立つ考え方です。これは不登校に対する1つの典型的な考え方であったし、歴史的に見てもかなり強くあったと言えます。無理してでも引っ張り出してもいいということもあったわけです。
これを図にしてみると、典型的な例として「A」にあたるところは、学校に行かせる方向で、原因論として家族や子どもの問題の方が大きいという認識に立つ考え方です。これは不登校に対する1つの典型的な考え方であったし、歴史的に見てもかなり強くあったと言えます。無理してでも引っ張り出してもいいということもあったわけです。
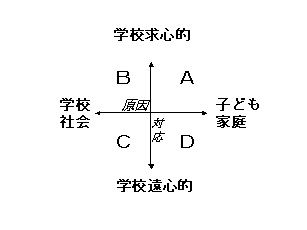 これを図にしてみると、典型的な例として「A」にあたるところは、学校に行かせる方向で、原因論として家族や子どもの問題の方が大きいという認識に立つ考え方です。これは不登校に対する1つの典型的な考え方であったし、歴史的に見てもかなり強くあったと言えます。無理してでも引っ張り出してもいいということもあったわけです。
これを図にしてみると、典型的な例として「A」にあたるところは、学校に行かせる方向で、原因論として家族や子どもの問題の方が大きいという認識に立つ考え方です。これは不登校に対する1つの典型的な考え方であったし、歴史的に見てもかなり強くあったと言えます。無理してでも引っ張り出してもいいということもあったわけです。