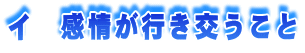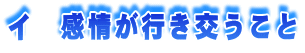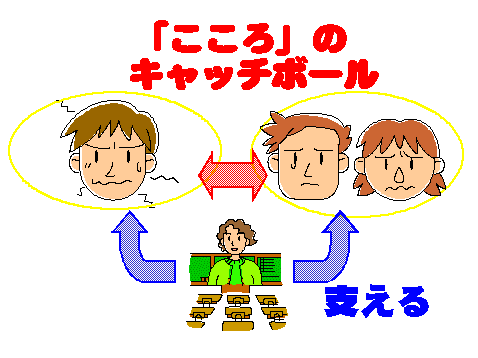特に小学校低学年の登校しぶりの子どもへの関わりにおいて、車で送ってきた母親から泣きじゃくる子どもを受け取って「後はすべて学校に任せてください、すぐに落ち着きますから、お母さんはもう帰ってください」ということがあります。
学校がこういう対応をすると、特に仕事を持つ母親はとても気が楽になり、「学校でのことなんだから、後のことは学校でお願いしよう」と考え、一見、親自身の安定が図られ、学校と家庭がうまく連携しながら子どもの自立を促すための関わりができているとそれぞれが思い込みがちです。
しかし、自分一人で抱えきれないほどの不安が押し寄せている「よい子」は、今こそ親との関わりを必要としているのであり、その子どもにしてみれば、学校は子どもと親を引き離すものとして存在することになります。
これは、子どものこころの成長を促すという名目のもとに、何ら子どものこころと周りの大人たちがこころを響き合わせることなく、学校と家庭が、学校不適応を起こしている「子どもを表面的にキャッチボール」している状態であるとも言えます。
登校時間になると学校はキャッチミットを広げ、親から子どもを受け取る、子どもはそうされまいといろいろな変化球を試します。
子どもは不定愁訴を訴えるなどして、学校に受け取られまいとするわけです。下校時間になると、学校は家庭にその日の子どもの表面的な様子、例えば「教室に1時間入れました」「休み時間に友達と遊べました」などを伝え、子どもを家庭に返すわけです。この関わりには「こころのキャッチボール」は存在しません。
|
おおよそ小学校低学年の時期は、子どもが安定して登下校できるまで親に横についていてもらう方が、不登校や登校しぶりの状態は改善されていくことが多いように思えます。学校は、子どもと親を離そうとするのでなく、この退行現象を「親子関係の修復のサイン」と受け止めて、これから互いに新しい関係を一緒につくろうとされるように仕向けていくことのほうが大事だと考えます。
|
Fig.3「こころのキャッチボール」 |
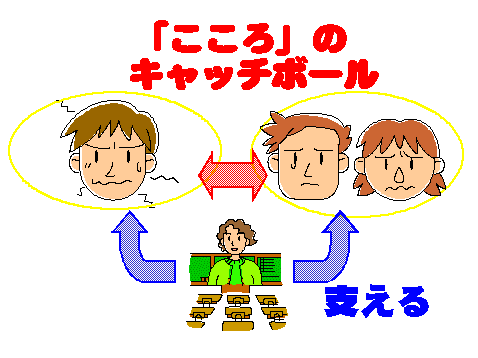 |
いわゆる「こころのキャッチボール」を行えるように仕向けていくことです。例えば、小学校低学年の子どもであれば、登校した後、子どもが落ち着くまで親が絵本の読み聞かせをするとか、抱っこしながら一緒にビデオを観るとか、隣の空き教室で待ってやるとか、そういう親とのゆったりしたかかわりの中で子どものこころに触れる、子どものこころから発せられたメッセージを受け取りそれに応えるという、親との「こころのキャッチボール」をするのです。その「こころのキャッチボール」を学校が支援することが大事です(Fig.3)。
学校においても個別にゆったりと関われる人的、空間的、時間的余裕があればなおさら、子どもとの関わりのなかで上述したような体験の中で起こる、溌剌としたあるがままのこころの表出を正面から本気で受け止め、それに応える体験を子どもと積み上げることが大事です。
その結果として「教室に1時間入れた」「休み時間に友達と遊べた」ということになるかもしれないわけで、「こころのキャッチボール」が学校や家庭でできるようになると、必ず子どもは変化してくるものです。子どもの年齢によってキャッチボールの内容は変わってきますが、「背のびしているよい子」の不登校の子どもへの関わりにおいては、年齢によらず基本的にこのことが極めて重要であると思われます。